 |
2003年10月18日・19日と大山酒造さんにお邪魔をして、伊佐大泉のできるまでをお邪魔をしながら、見学させて頂いて来ました。実際の作業の順序とは少し違いますが、芋焼酎の製造過程順にご紹介させて頂きます。 ご紹介している写真をクリックして頂くと、大きな写真を見る事ができます。 |
 |
 |
昔から行っている人力による洗米です。 以前は内地米を使用していたそうですが、現在は外産の破砕米を使用しているそうです。 |
 |

 |
|
 |
蒸しあがった米を、大きなザルにのせて「エッサ、ホッサ」と運びます。頭が結構痛い! それを広げて、麹菌をまぶせる温度まで下げていきます。 |
---------温度よし。いよいよ麹菌を混ぜ込みます---------
 |
まず、タンクに水を入れて、そこに先ほど用意した米麹を入れていきます。手早くさっさと作業します。 更にそこに酵母を入れ温度を管理しながら、1次モロミの出来上がりを待ちます。 麹菌の持つ酵素により、米のデンプンをブドウ糖に変え、そのブドウ糖を酵母がアルコールに変えます、この「糖化」「発酵」を約1週間行い、1次モロミが出来上がります。 |
 |
 |
 |
 |
小分けに袋詰めされた新鮮な芋が山積みになってます。 |  |
 |
ほとんど手作業に近い芋洗い機、洗った芋はベルトコンベア?で大きな蒸し器に入れられます。 | |
| 右の写真は蒸しあがったところ。結構美味しかったです。 |  |
|
 |
芋蒸し器で蒸した芋を大型タンクに移した1次モロミと水をあわせた物に破砕しながら混ぜていきます。 このとき片寄らないように、かき混ぜながら行います。 |
 |
 |
芋のデンプンにより更に発酵が進みますが、温度が上がらない様に温度管理をします。タンクの中の2つの筒は、中に水が流れていて熱を取って外に流れます。 | |
 |
できた2次モロミを別のタンクに移し蒸留まで管理します、蒸留まで約9日間。 |  |
 |
2次モロミタンクよりステンレス製の常圧蒸留器に2次モロミを移します。 蒸留器の小窓からモロミが見えます。 |
 |
 |
蒸気で加熱すると、蒸留がはじまります。どことなく焼酎の香りが漂います。 できた焼酎は左の装置を通って、地下タンクに貯められます。 |
|
 |
地下タンクから大型タンクに原酒が移され、飲み頃になるのを待ちます。 貯蔵中は原酒に含まれる油成分が上部に浮いてくる為、これを手作業で丁寧に取り除きます。 |
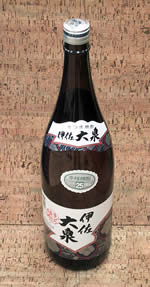 |
原酒をアルコール25度まで割り水をし、瓶詰めします。 これが皆さんの前に現れます。 お湯割最高!ロックも良し! |
 |
今回、大山酒造の社長さんをはじめ、杜氏さん、社長の奥様、蔵の皆様には大変御世話になりました。
これほど手による部分が多いとは、思ってもいませんでした。一層大事に飲んでいきたいと思っております。
ありがとう御座いました。これからも宜しくお願い致します。







